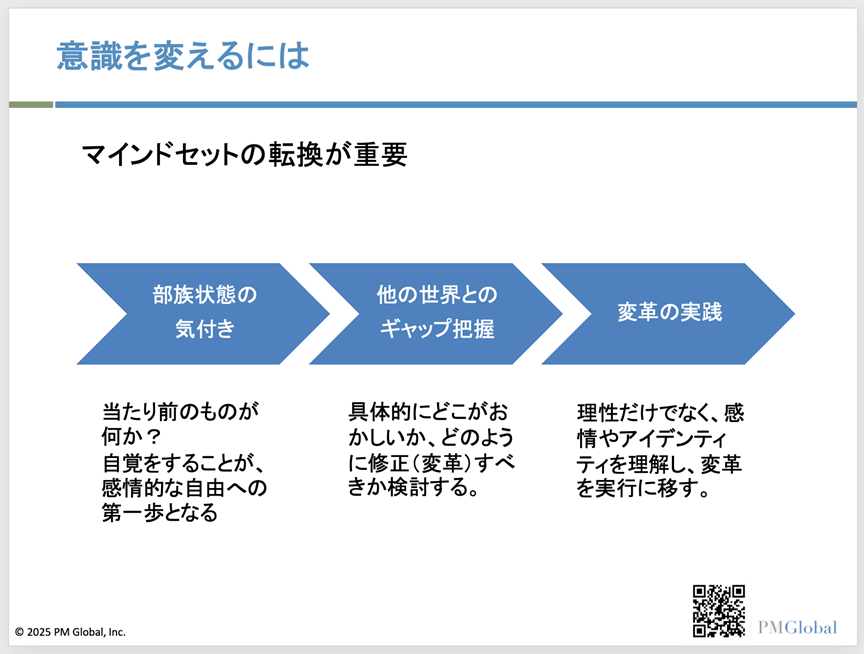グローバルのヒント
木暮知之のインサイト
「他者になりきれなかった…」から見えたこと
社内研修でイマーシブ・リアリティの手法を取り入れたことがあります。研修を無事終えて、参加者全員で内容を振り返る中で、とある社員が「(役に)なりきれなかった」と自己評価していました。
この社員に割り当られた役は、出世のためなら手段を選ばない、成功至上主義の営業部長。面倒な業務を部下に押し付ける一方、手柄は平気で横取りする自己中心的で無責任なパワハラ上司役でした。
社員は「粗暴に振る舞ったり、部下に厳しい口調で迫ったりできなかった」と振り返っていました。研修でわれわれが目にしたのは、自分の要求を部下が受け入れるまで言葉で執拗に迫る上司。怒鳴ったり机を叩いたりして相手を威圧するのではなく、いわばネチネチと相手を攻撃するタイプでした。
粗野な言動がとれなかったのは、自分の価値観とは異なる行為に対する心理的な抵抗があったり、相手の誤解を避けたいという自己防衛の気持ちが働いたりしたのが一因かもしれません。無意識のうちに自分の癖や価値観、行動傾向がキャラクターに反映されてしまったため、思い描いていた当初の役柄のイメージとギャップが出たのでしょう。

この社員は利己的に行動しがちな人の思考回路を想像し、自己中心的な人物になる体験をしました。思い描いていたキャラクターと実際の自分が表現したパワハラ上司に差を感じることで、自身が大切にしている価値観や行動様式にも気付くことができました。つまり、他人を理解する試みから自分自身に対する新たな気づきも得られた。イマーシブ・リアリティでは「他者理解」だけでなく「自己理解」も深められます。
社内研修テーマの1つは「パワハラのリアル」でした。部下役だった別の社員は、この上司の言動について「プレッシャーを受けた」「ストレスに感じた」とコメントしていました。部下を罵ったり人格を否定したりしなくても、身の回りにいそうな皮肉っぽい上司として、部下へのパワハラは機能していたのです。
パワハラ上司になりきれなかったと思っていても、部下には十分なストレスだったことからも分かるように、ハラスメントは相手がどう感じるか、が非常に重要です。よく聞くような「自分は理解のある上司だから大丈夫」「相手を傷つける発言なんて、したことがない」という自己評価は、あまり当てにならないことも再確認できました。(了)
いかがでしたか。イマーシブ・リアリティ研修について、もっと知りたい方はこちらからお気軽にお問い合わせください。